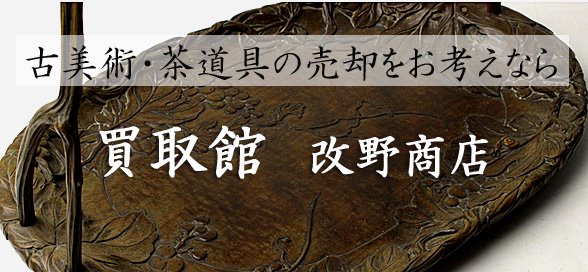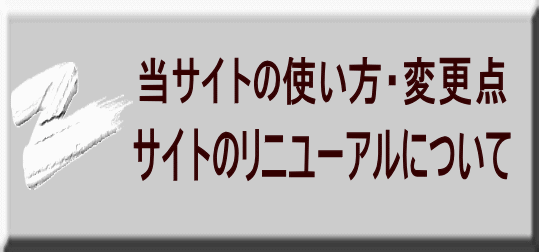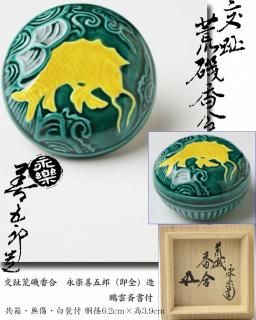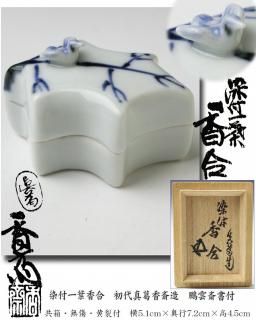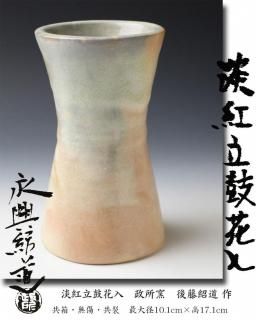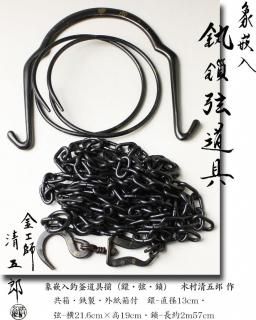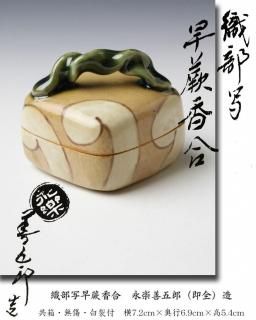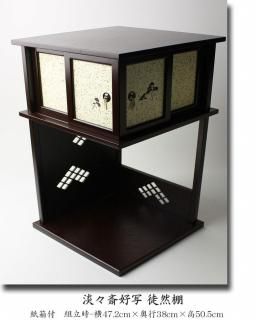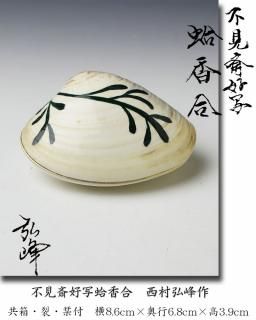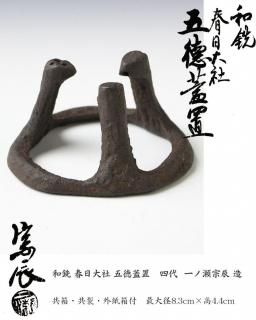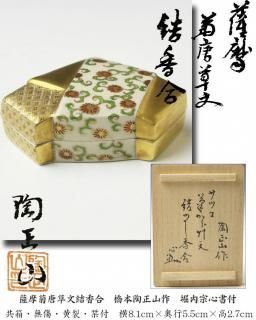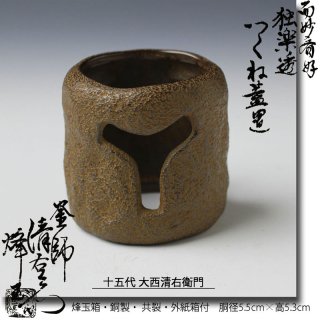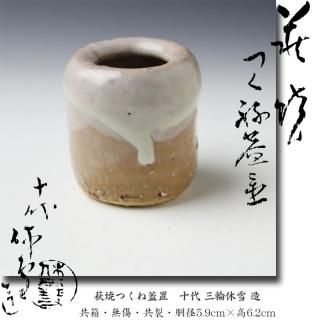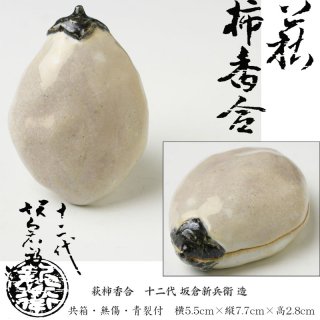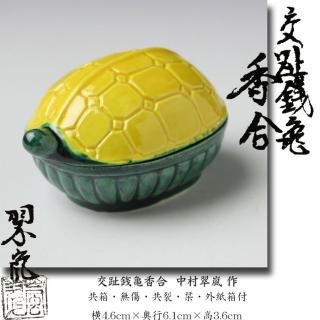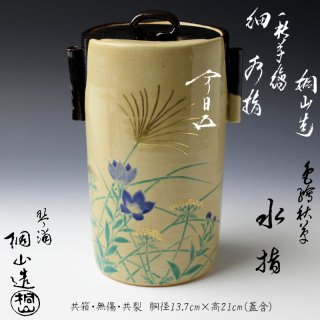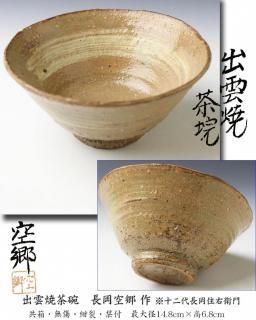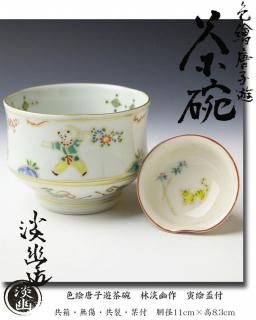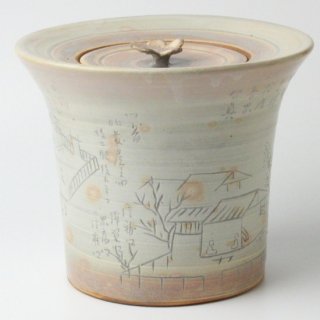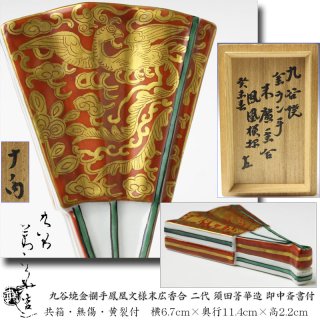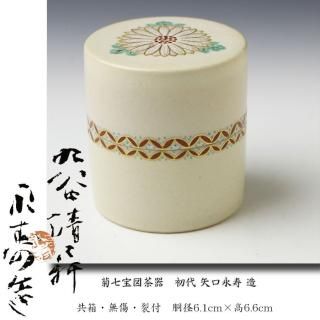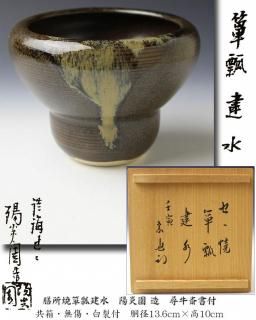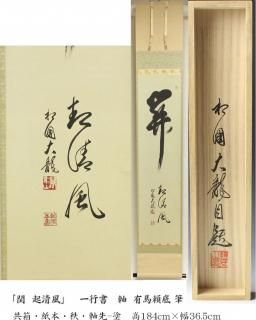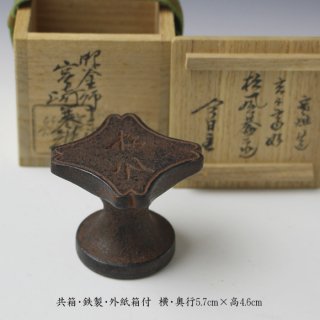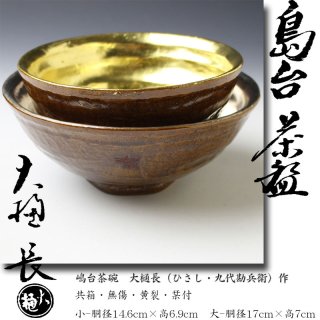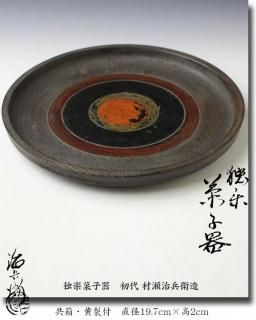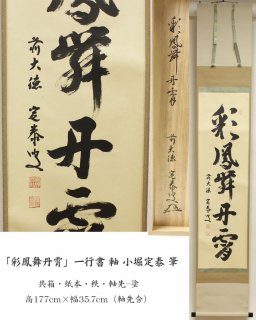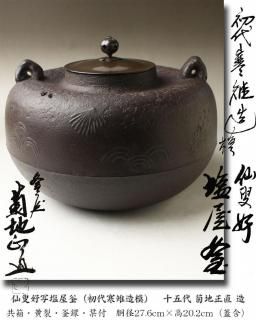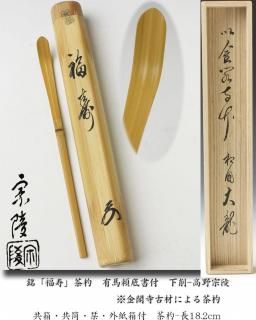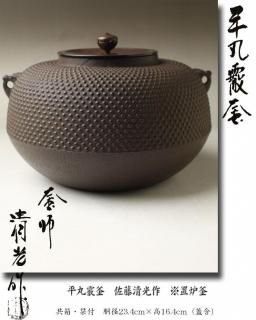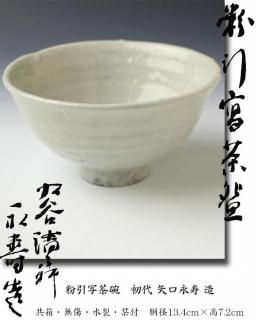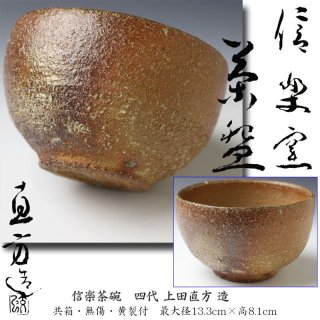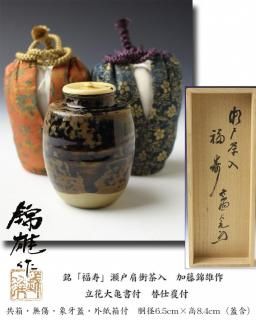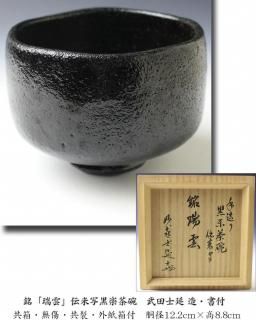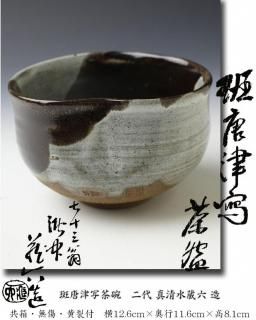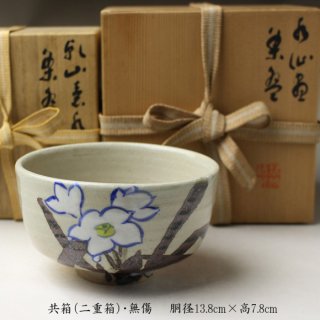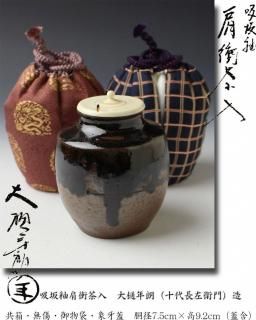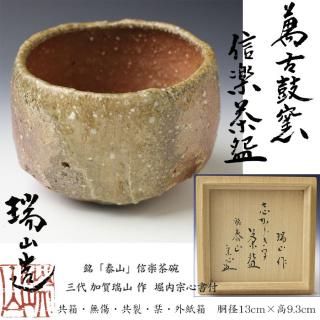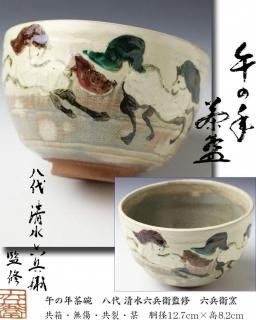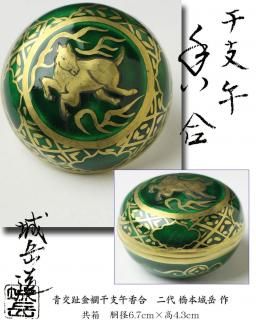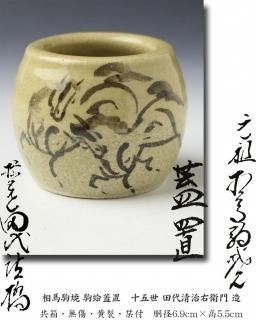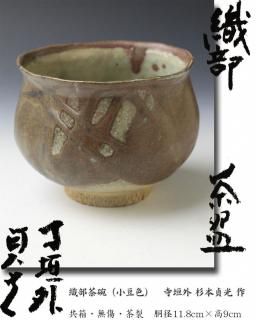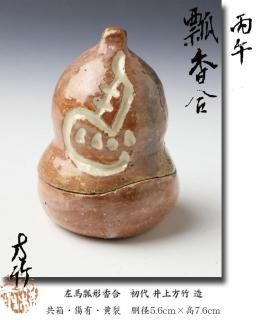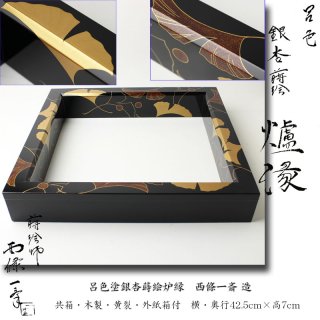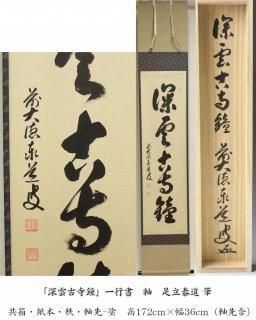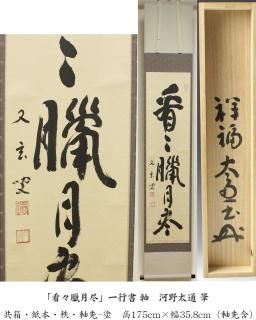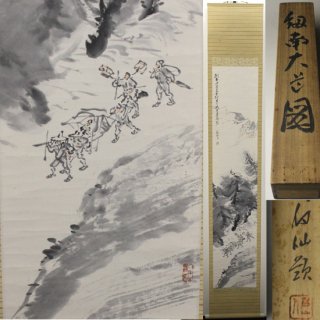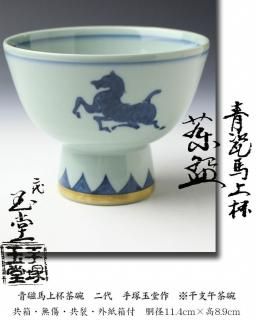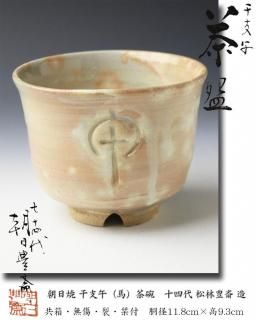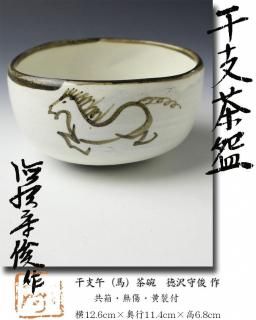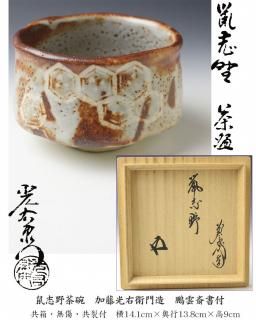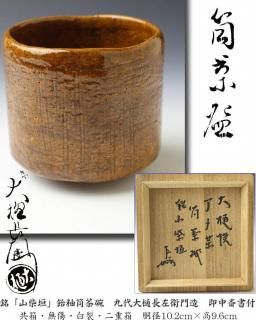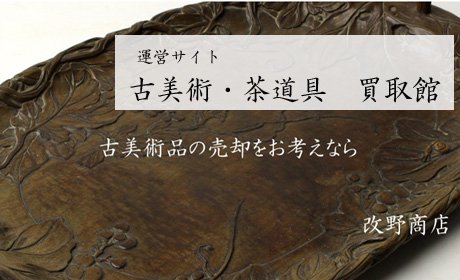京都府
-
 鶴香合 岡本漆専堂作 尋牛斎(久田宗也)好・書付
鶴香合 岡本漆専堂作 尋牛斎(久田宗也)好・書付 SOLD OUT
◇岡本漆専堂・・京都を代表する老舗の漆器店。
SOLD OUT
◇岡本漆専堂・・京都を代表する老舗の漆器店。
◇表千家・尋牛斎(久田宗也)宗匠の御好みで書付があります。
◇作品は、状態良好です。(指摘あり)
◇30年前頃の作品です。
◇十二代 久田宗也(尋牛斎)・・大正14年、生まれ。表千家流久田家12代。表千家13代千宗左にまなぶ。表千家流茶道教授として活躍。博識で知られ,「茶の道具」「茶の湯用語集」などの著作がある。不審庵理事をつとめた。平成22年没。85歳。京都出身。京大卒。 -
 宝尽し金銀象嵌蓋置 十一代 中川浄益 造
宝尽し金銀象嵌蓋置 十一代 中川浄益 造 68,000円(内税)
◇中川浄益(十一代)・・大正9年生。昭和15年、十一代浄益襲名。千家十職。平成20年、没。
68,000円(内税)
◇中川浄益(十一代)・・大正9年生。昭和15年、十一代浄益襲名。千家十職。平成20年、没。
◇鉄地に宝尽し金銀象嵌が三方向にあり、出来がよいです。
◇作品、きれいで状態良好です。箱は経年感あり。
◇30年〜40年前頃の作品 。 -
 独楽繋ぎ蒔画大棗 九代 西村彦兵衛(象彦) 作 而妙斎書付
独楽繋ぎ蒔画大棗 九代 西村彦兵衛(象彦) 作 而妙斎書付  SOLD OUT
◇西村彦兵衛(九代)・・昭和40年、象彦を継承する。皇居新宮殿の玉座の塗加工、伊勢神宮第62回式年遷宮における御神宝調製にも携わる。
SOLD OUT
◇西村彦兵衛(九代)・・昭和40年、象彦を継承する。皇居新宮殿の玉座の塗加工、伊勢神宮第62回式年遷宮における御神宝調製にも携わる。
◇表千家・而妙斎宗匠の書付があります。一閑塗ですので、軽いです。
◇きれいで状態良好です。
◇20年前頃の作品。
◇而妙斎・・昭和13年、生まれ。表千家14代家元。13代即中斎の長男で、昭和42年に大徳寺の方谷浩明老師より「而妙斎」の号を与えられて宗員となる・・ -
 雪笹絵茶碗 二代 宮川香雲 作
雪笹絵茶碗 二代 宮川香雲 作 55,000円(内税)
◇宮川香雲(二代)・・昭和13年、京都生。父は宮川香斎から分家した龍谷焼初代宮川香雲。昭和55年、二代香雲を襲名。現在、三代目。
55,000円(内税)
◇宮川香雲(二代)・・昭和13年、京都生。父は宮川香斎から分家した龍谷焼初代宮川香雲。昭和55年、二代香雲を襲名。現在、三代目。
◇笹に積もった雪が感じよい茶碗です。
◇作品は、きれいで状態良好です。
◇30年〜40年前頃の作品。 -
 仁清金雲松鶴茶碗 加藤利昇 作
仁清金雲松鶴茶碗 加藤利昇 作 43,000円(内税)
◇加藤利昇(三代)・・昭和21年、二代・利昇の長男として京都に生まれる。永楽即全の絵付師と活躍した後、昭和54年に三代利昇を襲名する。同60年、京都市伝統美術功労賞受賞。平成元年、京都高島屋にて個展他。
43,000円(内税)
◇加藤利昇(三代)・・昭和21年、二代・利昇の長男として京都に生まれる。永楽即全の絵付師と活躍した後、昭和54年に三代利昇を襲名する。同60年、京都市伝統美術功労賞受賞。平成元年、京都高島屋にて個展他。
◇よく描かれた華やかな作品です。
◇きれいで状態良好です。
◇20〜30年前頃の作品。 -
 交趾 蕗の薹香合 山本一如 作
交趾 蕗の薹香合 山本一如 作  11,000円(内税)
◇山本一如・・ 昭和24年 大阪に生まれ。初代中村翠嵐に師事する。総本山仁和寺顧問。真言宗御室派中山寺住職・杉本勇乗氏より「一如」と命名される。京都清水焼展グランプリ。京都清水焼展通産大臣賞他。
11,000円(内税)
◇山本一如・・ 昭和24年 大阪に生まれ。初代中村翠嵐に師事する。総本山仁和寺顧問。真言宗御室派中山寺住職・杉本勇乗氏より「一如」と命名される。京都清水焼展グランプリ。京都清水焼展通産大臣賞他。
◇大きさは、小振りです。
◇作品は、きれいで状態良好です。
◇30年前頃の作品。 -
 黒真塗五重縁高 川瀬表完 作
黒真塗五重縁高 川瀬表完 作 SOLD OUT
◇川瀬表完・・昭和12年、京都生。父・初代表完に師事。兄・表完(本名・厚)とともに二代表完を名乗り、京塗りを受け継ぐ。京漆器伝統工芸士。
SOLD OUT
◇川瀬表完・・昭和12年、京都生。父・初代表完に師事。兄・表完(本名・厚)とともに二代表完を名乗り、京塗りを受け継ぐ。京漆器伝統工芸士。
◇表完さんらしい、しっかりした黒真塗の縁高です。
◇中は、特に問題なく状態良好で、底面は、多少畳スレがありますが、仕方がない程度です。基本的に良い方です。
◇30年前頃の作品です。 -
 仁清写 鶴香合 手塚桐鳳 作
仁清写 鶴香合 手塚桐鳳 作 SOLD OUT
◇手塚桐鳳(とうほう)・・京焼の手塚石雲(充)が監修した窯作。
SOLD OUT
◇手塚桐鳳(とうほう)・・京焼の手塚石雲(充)が監修した窯作。
◇可愛らしい鶴の香合です。
◇作品は、きれいで状態良好です。
◇20年前頃の作品。 -
 青華開扇香合 大丸北峰 造
青華開扇香合 大丸北峰 造 10,000円(内税)
◇大丸北峰(二代)・・大正5年、生まれ。先代北峰・清水六兵衛に師事する。京展、全関西展ほか審査員。京都工美協理事。
10,000円(内税)
◇大丸北峰(二代)・・大正5年、生まれ。先代北峰・清水六兵衛に師事する。京展、全関西展ほか審査員。京都工美協理事。
◇雰囲気のある香合です。
◇作品は、状態良好です。箱は経年感あり。
◇50年前頃の作品。 -
 銘「薄氷」茶杓 有馬頼底書付 下削-谷村弥三郎
銘「薄氷」茶杓 有馬頼底書付 下削-谷村弥三郎 25,000円(内税)
◇有馬頼底・・昭和八年東京生。大龍窟と号す。相国寺専門道場に掛錫、大津櫪堂に師事。同43年相国寺塔頭大光明寺住職、平成七年相国寺派管長に就、同時に金閣寺、銀閣寺住職を兼ねる。
25,000円(内税)
◇有馬頼底・・昭和八年東京生。大龍窟と号す。相国寺専門道場に掛錫、大津櫪堂に師事。同43年相国寺塔頭大光明寺住職、平成七年相国寺派管長に就、同時に金閣寺、銀閣寺住職を兼ねる。
◇しぼ竹を使われた茶杓で、薄氷のような景色があり、銘にぴったりです。
◇作品はきれいで状態良好です。
◇30年前頃の作品。
◇谷村弥三郎・・奈良県生駒市の竹芸師。 -
 お多福香合 六兵衛窯
お多福香合 六兵衛窯 SOLD OUT
◇京焼の八代・六兵衛窯の作品です。
SOLD OUT
◇京焼の八代・六兵衛窯の作品です。
◇可愛らしい、お多福香合です。
◇作品は、状態良好です。
◇10年前頃の作品です。 -
 金地白梅図茶碗 山川敦司 作
金地白梅図茶碗 山川敦司 作 SOLD OUT
◇山川敦司・・昭和37年京都に三代山川巌の長男として生まれる。同57年京都府立陶工訓練所に入所。昭和58年京都市立工業試験所に入所。昭和61年、伝統工芸近畿支部展入選。平成20年、伝統工芸士に認定他。
SOLD OUT
◇山川敦司・・昭和37年京都に三代山川巌の長男として生まれる。同57年京都府立陶工訓練所に入所。昭和58年京都市立工業試験所に入所。昭和61年、伝統工芸近畿支部展入選。平成20年、伝統工芸士に認定他。
◇表面は金地で大きく梅の花が描かれて、感じよいです。
◇きれいで状態良好です。(指摘あり)
◇平成20年以後の作品。(栞より)